|
|
■今回の道程 (約10㎞) (私の万歩計約26,200歩) JR川崎駅・・稲毛神社・・砂子交差点~佐藤本陣跡~小土呂橋~芭蕉句碑~八丁畷~熊野神社~市場一里塚~鶴見橋関門跡~生麦魚河岸通り~キリンビアビレッジ(昼食)~生麦事件碑~オランダ領事館跡~高札場跡 JR川崎駅・・稲毛神社・・砂子交差点~佐藤本陣跡~小土呂橋~芭蕉句碑~八丁畷~熊野神社~市場一里塚~鶴見橋関門跡~生麦魚河岸通り~キリンビアビレッジ(昼食) |


稲毛神社は、明治より前は、「川崎山王社」という名前でした。今でも地元の年配の方々は「山王さん」と呼んでいるそうです。 社伝によりますと欽明天皇の時代(6世紀頃)に鎮座したといわれています。また、『新編武蔵風土記稿』の記述では、源頼朝の時代、佐々木高綱が奉行になり、社殿を造営したと伝えられています。 境内には1729(享保14)年6月、田中本陣の田中休愚の一族、手代衆などが奉納した手洗石、1742(寛保2)年の大雨による洪水で壊れ、流失した小土呂橋の一部が保存されています。 |





この手洗石は田中休愚と川崎宿との深い係わりを物語る貴重な遺品の一つです。 |

| ご神木の大銀杏は、樹齢約1.000年といわれています。江戸時代には東海道を旅する人たちから「山王様の大銀杏」と大切にされ、旅の目印にもなっていました。 左下隅の車と比べてみてください。 |


惣之助が一躍有名になったのは、当時、流行歌といわれた歌謡曲の作詞家として作詞した、「男の純情」「人生劇場」「人生の並木道」「青い背広で」「緑の地平線」などの曲が大ヒットしてからでした。 なお、佐藤本陣は、この記念碑のある交差路の向かい側にあったといわれています。 |
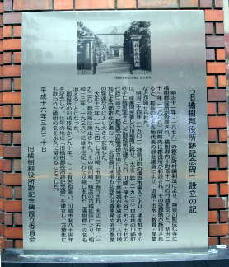

1901(明治34)年、神奈川町の横浜市編入により郡内の中心は川崎町に移りました。1913(大正2)年、今の川崎町に威風堂々とした郡役所の建物ができました。1924(大正13)年に川崎町が市制を敷き、1926(大正15)年、郡役所は廃止、1938(昭和13)年には半世紀にわたり親しまれてきた「橘樹郡役所」の名が消えました。 |




この「こゝに幸あり」の記念碑は、老人ホームが地域貢献と高齢者の安らぎの場となることを願い開設10年を機に建立した、と説明板に記されていました。 |


俳聖松尾芭蕉の足跡を見ることのできる句碑が、京浜急行電鉄の八丁畷(はっちょうなわて)駅近くの旧東海道沿いに建立されています。 1694(元禄7)年5月、江戸深川の「芭蕉庵」に住んでいた芭蕉は、故郷の伊賀(今の三重県)に帰るため旅に出ました。師匠の芭蕉との別れを惜しむ江戸の弟子たちは六郷川(今の多摩川)を渡り、川崎宿まで見送りにきました。八丁畷にあった茶店「榎だんご」で最後の別れを惜しんだといわれています。このときに詠んだのがこの句でした。 長旅をしていた芭蕉は、途中の大阪で病に倒れました。、 「旅に病んで 夢は枯野を かけめぐる」 この辞世の句を残して同年10月12日、俳句一筋の人生の幕を下ろしました。51歳のときでした。 この句碑は没130年後の1830(文政13)年8月、俳人一種が俳聖芭蕉の道跡を偲び建立したものです。 |

芭蕉の句碑の横から見たところです。前方は京浜急行電鉄の八丁畷駅です。旧東海道は踏切を渡り左に向かいます。 |

東海道は川崎宿を過ぎると隣村の市場村に入りますが、この間はおよそ八丁(約870メートル)あります。畷とは田畑の中の真直ぐの道のことをいいます。それで「八丁畷」と呼ぶようになりました。 この地では江戸時代より多くの人骨が見つかっています。戦後の道路工事などによる掘削でも見つかり、その数は十数体になります。 江戸時代の記録では震災、大火、洪水、疫病などに見舞われ、その犠牲者を宿のはずれの松や欅の並木の下にまとめて埋葬したのではないかといわれています。1934(昭和9)年、地元と市が相談をして犠牲者の霊を供養するため慰霊塔を建立しました。 |


赤穂浪士ゆかりの宮大工が造営したといわれています。境内には江戸時代の俳人の句碑があります。 境内には樹木が数えるほどしか見られず、神社仏閣の静寂さを感じられなかったのは残念でした。 |

| いちば銀座という商店街のアーチ看板がありました。ここは旧市場村の中心だったのでしょうが,店は点在化して活気がなく世の移り変わりを感じてしまいました。 この辺りから暫く歩くと、市場一里塚跡、鶴見川橋と続きます。 |
ここで気になったのが大きな石碑の横に鎮座している双体地蔵でした。当初からここにあったものなのでしょうか、それとも村内の別の場所にあったものなのでしょうか。とてもよい表情をしていました。 |






近代的でモダンな橋を渡って下り道を少し歩いたところに「鶴見橋関門旧蹟」の碑が立っています。 1859(安政6)年、横浜開港に伴い外国人の身辺保護のため、神奈川奉行は横浜へ通じる主要道路の要所に関門・番所を設けて厳しい取締りをしました。 鶴見橋関門は1860(万延元)年4月に設けられました。1862(文久2)年8月生麦事件の発生により宿内に20ヶ所の見張番所が置かれました。関門・番所には宿役人2名、道案内3名などが置かれ警戒にあたりました。非常のときは半鐘を鳴らして隣りの関門・晩所と連絡をとっていました。 明治時代に入り世の中も安定してきたため1871(明治4)年11月に関門・番所はすべて廃止されました。 |



毎年4月29日にはおよそ700年前から伝承されている民俗芸能「鶴見の田祭り」が盛大に行われています。 |
 →
→ 

 →
→ 
 →
→ 
 →
→ 
 →
→ 


この行事は端午の節句の行事といわれ、萱で作った大きな蛇体の雌雄2体を地元の青年、子供が担いで、「蛇も蚊も出たけ、日和の雨け、出たけ」と大きな声で唱えながら担ぎ、絡み合いをさせた後の夕方に海に流して無病息災を祈ったということです。 行事の形式などは変わっているそうですが、今も行なわれています。 |



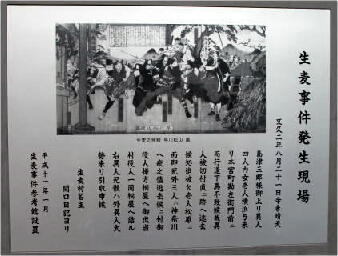



|