| |||||||
| |||||||
■今回の道程 (約10㎞) (私の万歩計約19,500歩) 日本橋(日本国道路元標・高札場跡・魚河岸跡)〜安藤広重旧居跡〜京橋(江戸歌舞伎発祥の地)〜旧京橋擬宝珠〜銀座発祥の地〜芝大神宮(だらだら祭りで有名)〜増上寺(徳川家菩提寺)〜金杉橋〜勝海舟・西郷隆盛会見の地碑(薩摩藩屋敷跡)〜札の辻〜高輪大木戸跡〜泉岳寺(赤穂城主浅野氏菩提所・四十七士の墓)〜JR品川駅 芝大神宮(だらだら祭りで有名)〜増上寺(徳川家菩提寺)〜金杉橋〜勝海舟・西郷隆盛会見の地碑(薩摩藩屋敷跡)〜札の辻〜高輪大木戸跡〜泉岳寺(赤穂城主浅野氏菩提所・四十七士の墓)〜JR品川駅 |



この芝大神宮は実際に起きた火消しのめ組の者と力士の喧嘩を題材に脚色した歌舞伎狂言の「神明惠和合取組」の舞台として知られています。また、毎年9月中旬に10日間続くお祭りは「だらだら祭り」と呼ばれ賑わいをみせています。 |






浄土宗の大本山で徳川将軍家の菩提寺として栄えた名刹です。慶長16(1611)に建立された山門(三解脱門)は、入母屋造本瓦葺二層朱塗りの楼門で、国の重要文化財に指定されています。震災と戦災により境内の建造物の多くは焼失してしまいました。 |








ここには、二代・忠秀、六代・家宣、七代・家継、九代・家重、十二代・家慶、十代・家茂の6将軍と皇女和宮の墓が祀られています。 |


古川に架かる金杉橋。昔はこの辺りまで海岸でした。東海道が開通したときの起点は金杉橋南側の本芝一丁目に定められました。その後増上寺周辺の海岸が埋め立てられため東海道も延長され、起点が日本橋に移されました。金杉橋までが江戸市街とされ馬宿、旅籠が軒を並べ賑わいました。古典落語「芝浜の財布」に出てくる芝浜という地名はこの辺りといわれています。 |





ここは旧薩摩藩蔵屋敷跡です。明治維新の江戸城総攻撃直前の慶応4(1868)年3月14日、陸軍総裁の勝海舟は東征軍参謀の西郷隆盛と会見しました。およそ・100万の江戸市民を維新の戦火から守るため「江戸無血開城」を実現させるためでした。会見の結果、江戸無血開城の取り決めが実現、江戸市民100万の生命・財産が守られました。この年の9月8日、「明治」に改元されました。10月13日には天皇が東京入り、江戸城を「東京城」に改称して皇居としました。 |


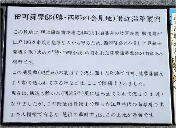
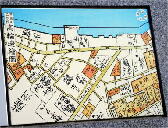





高札場のある辻で、元和2年(1616)、江戸入口として芝口門を設けました。「札の辻」とは高札場が賑わいのある街道の分岐する場所に置かれたためについた地名で全国各地にみられます。 |

札の辻を過ぎて暫く歩くと元和キリシタン処刑地跡があります。東海道の入口に当たるこの辺りは、鈴ケ森刑場ができる以前の晒し場でした。 |




木戸は街道の両側に石垣などを築き、夜間は閉めて通行止めにしました。木戸は治安の維持と通行規制の二つの大きな機能を持っていました。 高輪大木戸は江戸の南の入口として当時の東海道の道幅約六間(10m)の両側に石垣を築いて造られました。当初は宝永7年(1710)芝口門に建てられましたが享保9年(1724)に現在地(三田3丁目)に移されました。 この木戸では、京上り、東下り、或いは伊勢参りなど人々への送迎が行われていました。辺りには茶屋などがあり、海岸の景色もよく賑わいをみせたといわれています。 現在ある石垣は海側の部分で、長さ7.3㍍ 幅4.5㍍ 高さ3.6㍍ あります。 |



泉岳寺は慶長17年(1612)に徳川三代将軍家光の禅学の師、宗閑の隠居寺として創建されました。火災で焼失したため家光の命により浅野家はじめ6大名が寛永18年(1641)に現在地へ再建しました。江戸にある曹洞宗3ヶ寺の一つに数えられた名刹でした。 この泉岳寺が江戸市中に知られることになったのが赤穂浪士の討入りでした。元禄14年(1701)赤穂藩の浅野内匠頭長矩は殿中松の廊下で吉良上野介義央へ刃傷におよび切腹、翌15年12月14日大石内蔵助良雄以下47名は吉良邸に討入り上野介の首をとり、主君の恨みをはらしました。主君と奥方、内蔵助以下四十七士の墓は今日でも手向けられる線香は絶えることはありません。 |















| |||||||
| |||||||