|
|
| �s���@--km�@�@���̖����v�@--,---�� �@�`�O����Ёi�������䂩��̈ɓ��̈�̋{�j�`�≮��Ձ`�~�����`�{�w�Ձ`���̏��`�ɓ��������Ձ`��є�`�����ꗢ�ˁ`�����_�Ёi�������Ƌ`�o�̑Ζʐj�`�����T��(�\��Z��̋w��������ɓo�ꂷ��T�ߕP�̔�)�`�T���Y(���Ô˓���)�`����n���`���Èꗢ�� |


�@�����ɂ́u���������g���̔�v������܂��B1180�i����4�j�N�W��17���A�������͎O����Ђɐ폟�F��������q����������铢�����Ƃ����܂��B �@�܂������m�Ԃ�1694(���\7)�N5���Ō�ƂȂ������ʼnr�傪���܂ꂽ���A��R�q���̉̔肪����܂��B |


 �@���@
�@���@
| �q�a�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�a |
 |  ������ �k�𐭎q���|�� �����l�N�܌������������ƒǓ��̐S������߂ĕS���̓��Q�������܁@�����|���ċx�������Ɠ`������@�E���͖k�����q�̍��|�����ł��� �ʐ^���F�������̗��� |
 �@�@�@
�@�@�@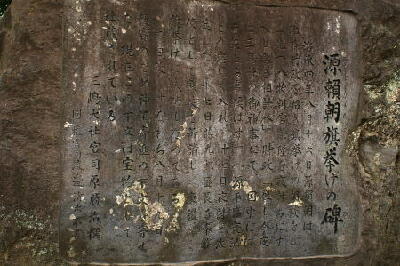

| �m�ԋ�� �@ �ǂނ݂�Ɓ@����@�J�́@�ԓ܂� ���Ƃ́m����n�̎��Ō��\���N�i1694�j�܌��\�l���O�����_�ɎQ�w�����m�Ԃ͉J��ɐ_�r�̕ӂ肹��̉Ԃ̌Q�����ō]�˂Ɏc���Ă����a���̍ȁu���āv�̐g���Ă��ĉr��ł��� �@�i���������p�j |

| ��R�q���̉̔� �@�̂����Ȃ�@�O���̂܂��̂����ԉ� �@ ����̂���Ɂ@�U��ď���Ȃ� ��R�q���͋z���{�茧�ɐ��܂�吳��N�i1920�j�O���s�̐��ׂ�̏��Îs���тɏZ�ݔ����\�ܓ��ɍs��ꂽ�O����Ђ̉čՂ�̉ԉ����Ă��̉̂��r�� �@�i���������p�j |



 �@�@
�@�@
�@�X�����s���ƉE���ɒ������X�ǂ�����܂��B�����̘e�̓��ɓ������Ƃ���ɖ≮��Ղ������Β��Ɛ���������܂��B �@�≮��͍��̎O���s�����������ʊٕӂ�ɂ���܂����B |

�@���̖�́A�]�ˎ���ɏ��喼���O���h�h������ۂɁA���܂�悤�w�肳��Ă����h�ł��鋌����{�w�̕\�傪�~�����Ɉڒz����Ă������̂Ɠ`�����Ă���B �i�ȉ��ȗ��E���������p�j |
 �@�@
�@�@
�@��y�@�������B �@���̖�́A�]�ˎ���ɏ��喼���O���h�ɏh������ۂɁA���܂�悤�w�肳��Ă����h�ł��鋌���Ö{�w�̕\�傪���~���Ɉڒz����Ă������̂Ɠ`�����Ă��܂��B |
 �@�@
�@�@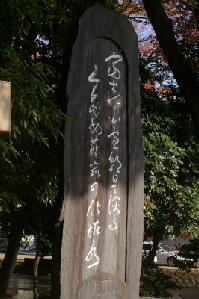
�@���Ɍ������ĊX���̍����ɔ���{�w�A�߂��̉E���ɐ��Ö{�w������܂����B |
 �@�@
�@�@
���F����{�w�Ղ̐����ł��B�@�@�E�F���̕ӂ�ɐ��Ö{�w���������悤�ł� |
�@�Ȃ��N���Q�����������������{�ʓ@�̉�V���뉀�A�y�����i�V�R�L�O���j�͖��뉀�Ƃ��Ēm���Ă��܂��B |
 �@�@
�@�@
�@���̏��͌����q�����Ԃɂ���O�ΐ_�Ћ����Ɍ����Ă��܂��B �@�]�ˎ���ɂ͏h��̐l�X�Ɂu�����Z�v�A�u���Z�v�̎���m�点�Ă��܂����B���̞����͑����m�푈��ɑ���ꂽ���̂ŁA���a�R�O�N���܂Œ��̘Z���Ɨ[���̘Z���ɏ��͓˂���Ă����悤�ł��B |
 �@�@
�@�@
�����ɂ͓����n�����A�u�m�ԘV����v�̔�A���Ȃǂ������Ă��܂��B |

 �@�@
�@�@

�@�O���L���H�w���߂��ĊX������E�ɂQ�O�O���[�g���قǓ������Ƃ���ɂ���܂��B�R��ɂ́u�ɓ��������v�̖��̎D�������Ă��܂��B�{������̈�p����������A�������̌����̂������̑傫�ȑb�����сu�ɓ������������v�̔肪�����Ă��܂��B |
 �@���@
�@���@
 �@�@
�@�@

|